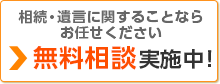遺言書があった場合

誰が何を相続するのか、相続において最も尊重されるべきものは被相続人の意思です。
被相続人が遺言書を残していた場合、基本的には遺言書の通りに相続が行われるため、まずは遺言書の有無を確認することが大切です。
ここでは、遺言書が発見された場合の相続手続きについて、解説させていただきます。
自筆遺言だった場合
たとえ家族であっても遺言書を勝手に開封することはできません。
これは遺言の内容が発見者によって改ざんされることを防ぐために法律で定められています。
遺言書は家庭裁判所に提出し検認の請求をし、相続人等の立ち合いのもとで開封されます。
家庭裁判所に提出する前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が課せられる他、ほかの相続人から改ざんを疑われたりトラブルの原因になります。 遺言書を見つけても慌てて開封しないよう気をつけてください。
また、誤って開封してしまった場合でも遺言書が無効となるとは限りません。開封してしまっても、検認の手続きは必要となります。
家庭裁判所に提出した後の流れ
- 家庭裁判所から検認を行う日の連絡がくる
- 指定された日に家庭裁判所に赴き、検認に立ち会う
- 検認では遺言の内容や日付を確認
- 基本的に遺言に従い相続手続きを進める (遺言書に遺言執行者が指定されていた場合、遺言執行者が相続手続きを進めます。)
公正証書遺言だった場合
家庭裁判所での検認は不要です。
基本的に遺言に従い相続手続きを進めます。 (遺言書に遺言執行者が指定されていた場合、遺言執行者が相続手続きを進めます。)
遺言執行者がしていされていない場合、相続人の代表が手続きを進めます。
また、行政書士・司法書士・弁護士などの国家資格者に依頼し、手続きを進める方法もあります。 (遺言執行者に指定されている場合を除き、ファイナンシャルプランナー、不動産業、税理士が相続手続き(相続関係説明図作成、遺産分割協議書の作成)を有料で行うことはできません。)
遺言書に記載の無い財産がある場合
遺言書に記載のない相続財産は、相続人の協議によって遺産分割協議書を作成し、遺産を分割します。
しかし、遺言書にない財産を巡ってトラブルに発展してしまうケースも多いため、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。
遺言書の内容に納得ができない場合
話し合いを行う
相続人全員の話し合いで遺産分割協議書を作成し、遺言書に沿わない遺産分割を行うことは可能です。
ですが、この場合相続人全員の合意が必要です。
法的な手段をとる
遺言書によって法定相続分が侵されているような場合、相続人は法的に一定の相続分を請求する権利があります。
これを遺留分減殺請求と言います。
法定相続分が侵されていなくても、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行う方法があります。
相続手続き その他のコンテンツ
初回のご相談は、こちらからご予約ください
![]()
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
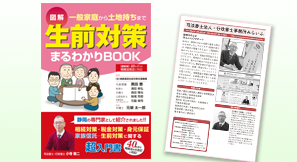
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました。